- 低地 (Shinchosha CREST BOOKS)/新潮社

- ¥2,700
- Amazon.co.jp
こんにちは。
今回記事にした、ジュンパ・ラヒリの『低地』ですが、かなり込み入った話なので手間取りました。そして手間取った挙句、どうしようもなくなったので、とりあえず、読んでくださるみなさんと、『低地』の物語の冒頭部分を一緒にツアーするという感じで書きたいと思いました。
帯にある、
「殺された弟。その妻とともに 生きようとした兄。」
この文章には、とてつもなく深いものがあります。兄が弟の妻に同情して一緒に生きる、というそんな安易なものではありません。僕はそう思って(某『永遠の○』みたいな話かと…)買ってしまい、平手打ちをくらった感じです。
では、ツアーの始まり。
みなさん、インドのコルカタ(旧カルカッタ(英))の南にあるトリーガンジ・クラブ(Tollygunge Club)をご存知でしょうか。英国人がインドを植民地としていた時代につくった大きなクラブらしいです。クラブハウス、テニスコート、競馬場、ゴルフコース、レストランにはビリヤードとブリッジの特別室、その中では蓄音機が音楽を流し、白い上着のバーテンが、ピンクレディーやジンフィズといった飲み物を出す。一方、そのクラブの外では、アディ・ガンガーが流れ、その岸にそってヒンドゥー教徒の集落ができています。また、コルカタの各所にもパキスタンからの避難民で溢れています。
また、この一帯には、二つの細長い池がありました。その奥に数エーカーの低地が広がっていて、モンスーンの季節のあとには二つの池の水位が上がり、低地にも水がたまって水浸しになることがあります。
この物語は、ガンディーの非暴力運動によりイギリスからインドが独立してから10年後の、この英国人クラブ、「トリーガンジ・クラブ」にベンガル人の兄弟、スバシュとウダヤンが忍び込むところから始まります。
そのとき、スバシュは13歳、ウダヤンは11歳でした。スバシュたちが、トリー・クラブの塀を乗り越えると、そこはゴルフ場でした。兄弟は初めてみるその光景に驚きます。
「こんな芝生をスバシュは見たことがなかった。カーペットのように均一に、ゆるやかな傾斜のある大地に草が広がる。砂丘の起伏、あるいは穏やかにうねる海とでもいおうか。きれいに刈り込んだグリーンには、手で押すと苔のような感触があった。……
……次第に余裕が出てきた。行く先に旗が立っている。地面に臍のような穴があってカップが埋まっているので、ここに球を転がすのだろうと思う。ところどころに浅くへこんだ砂地がある。フェアウェーに水たまりができていて、水滴を顕微鏡で見たようにおかしな形になっていた。」(『低地』p11)
スバシュの眼にはゴルフ場がこのように見えたのです。技法的に言うといわゆる異化というものでしょうか。兄弟の未知の世界の冒険の感覚が伝わってきます。
「インドの首相はネルーだが、ここの広間に飾られているのはイギリスの新女王エリザベス二世の肖像だ。」(『低地』p11)
何気ないセリフ、いやむしろちょっと意外なセリフと思われる方もいるかと思いますが、このセリフは兄弟の知り合いのビヒミラというイスラム教徒のセリフです。この人はインドとパキスタンが分裂した際に、イスラム教徒であるにも関わらず、インドに残ってこのトリー・クラブのゴルフ場でキャディをしているのです。インドとパキスタンの分裂に関しては、映画『ガンディー』などでも描かれています。ガンディーの失望感というものがよく出ていた作品だったのではと思います。
- ガンジー コレクターズ・エディション [DVD]/ソニー・ピクチャーズエンタテインメント
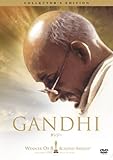
- ¥1,523
- Amazon.co.jp
トリー・クラブは兄弟の秘密の遊び場になります。鳥の羽やアーモンドの実を集めたりして遊んでいました。しかし、ある日、見回りの警官に兄弟は見つかってしまいます。ウダヤンは自分が忍び込もうと言ったと主張しますが、スバシュはスチール製のシャフトでお尻を殴られてしまいます。ウダヤンは兄をかばいます。警官はそれを見て立ち去りますが、兄弟はそれ以降、トリー・クラブに忍び込むことをしなくなりました。
その後、スバシュとウダヤンの性格や外見などの描写が生活を通して描かれます。スバシュは優等生タイプで大人しめな性格、ウダヤンは「やんちゃ坊主」とあります。外見は二人は似ていてよく間違えられることがある、肌の色は明るめの銅、体格も似ていて、なによりも声が似ています。
スバシュはウダヤンを待って、同じ年に学校に入学します。そこでトリー・ガンジの歴史を学びます。トリー・ガンジはウィリアム・トリー少佐がアディ・ガンガーの土砂を除いて運河にしたところから由来しています。この土地は元来、ジェネラル・バンク・オブ・インディアの頭取だったリチャード・ジョンソンの土地でした。この土地に一七八五年にルネサンス風の邸宅を建てています。さまざまな外来の樹木を、亜熱帯の各地からトリー・ガンジにもたらした等など。
二人は高校では光学、力学などを学び家庭内の配線を熟知します。モールス信号で遊んだりもします。大学はウダヤンがプレジデンシー大学、スバシュがジャダプール大学に進学します。世界の情勢も変化を見せ、このあたりから兄弟の進むべき道が分かれていきます。
「一九六四年。アメリカでは「トンキン湾決議」が採択され、北ベトナムへの直接攻撃が始まった。ブラジルでは軍事クーデターが発生した。
カルカッタの映画館では『チャルラータ』が封切られた。スリナガルの寺院で遺物の盗難事件があったのを機に、またしてもイスラム教徒とヒンドゥー教徒の争いが暴動になって百人以上が死んだ。二年前の中国との国境紛争をめぐってインド国内の共産主義勢力に対立が生じた。中国寄りで分派したグループはインド共産党マルクス主義派と称した。
デリーの中央政府では、いまだ国民議会派が実権を握っていた。この年の春、ネルーは心臓発作で死んだが、その娘インディラが入閣し、二年後には首相になる。」(『低地』p25)
一九六七年、ナクサルバリという土地に関するニュースが流れます。西ベンガル州ダージリン県の村です。そこは封建時代と大差ない暮らしをしていて富裕な地主階級に農民たちは搾取されていました。その土地でチャル・マズムダールとカヌ・サンヤルという共産主義活動家を中心に武装蜂起が起こります。警官隊と農民の衝突があり、11名が死亡、うち8名が女性でした。後にこのナクサルバリを発祥として、ナクサライトという共産党毛沢東派の武装テロ組織が勢力を持つことになります。このニュースを聞いた兄弟は話し合います。スバシュ「それで得るものはあるのかな。」ウダヤン「やっと立ち上がったんだ。必死の行動じゃないか。何もない人々、政権に守ってもらえない人々だ。」スバシュ「弓矢で近代国家に立ち向かう?」ウダヤン「あんな境遇に生まれたらどうすればいい?」
暗殺前にはマハトマ・ガンディーも参加していた国民会議派の政治が終わり、統一戦線に政治のイニシアティブは移っていましたが、インドの国内の情勢は変わりませんでした。労働者農民のための政治が行われず、革命派の農民に血まみれの弾圧が行われていました。非武装の農民たちを拘束し、従わなければ殺害しました。兄弟は打ちのめされますが、より打ちひしがれたのはウダヤンでした。「人々は飢えている。解決しようとするとこれなんだ。犠牲者なのに犯罪者にされている。撃ち返せないのに銃を向けられている。」
ウダヤンは中国の報道にあった字句を引きます。
「ダージリンに散った火花は燎原の火となって、必ずや広大なるインド全域を燃やすであろう」
ウダヤンは、日に日に左傾化していきます。スバシュはウダヤンの隠し持っていた小冊子を見つけます。そこにはマズムダールの記事があり、マズムダールは次のように主張していました。「インド革命が内戦の形態をとらざるを得ないと見るならば、地域単位で権力を掌握していく戦術しかあり得ないこともまた了解されるだろう」。その当時、中国では毛沢東が革命に成功していました。
ウダヤンとスバシュは大学院へと進学することになります。ウダヤンはカルカッタ大学に移り、スバシュはジャダプール大学に残りました。ウダヤンは反政府活動にのめり込んでいきます。それをスバシュは心配しますがウダヤンを止めることはできません。やがてウダヤンは工業高校の教師となり、スバシュはアメリカの博士課程に進むことになります。心だけでなく、地理的にも兄弟は離れることになります。
一九六九年、レーニンの誕生日に、インドに第三の共産主義政党が生まれます。ナクサライトの党員を中心とした勢力です。書記長にマズムダール、議長にサンヤルが指名されました。インドマルクス・レーニン主義派、略称CPI(ML)です。サンヤルは演説します。二〇〇〇年までには世界は解放される、人間が人間を搾取することから自由になる。マルクス主義、レーニン主義、毛沢東思想の世界的勝利を祝うであろう、と。スバシュはアメリカで海洋学を学ぶために旅立ちます。
スバシュはアメリカのロードアイランドに居住しました。このときのスバシュのアメリカについての想いを引が書かれた場面。
「この二つ(ロードアイランドとトリー・ガンジ)の場所は、あまりにも隔たりが大きく、心の中へ同時におさめておけないような気がする。新しい巨大な国のどこにも、古い国が住み着く余地はなさそうだ。両者をつなぐものはない。あるとすれば彼自身で、ほかにはない。ここへ来てから生きることに邪魔が入らなくなった。襲いかかってくるものがない。ここに住む人は、まるで背中に火がついたように押し分けかき分け突き進むことをしなくていい。」(『低地』p49~50) *()内はともすけ
スバシュは白い木造の家に部屋を借りました。リチャードという社会学専攻で歳は30ばかりの男とキッチンとバスルームを共用します。彼はクェーカー教徒の家で生まれ、大学では大学新聞に論説を書いたりして少し過激な男なのです。彼はガンディーは自分にとってヒーローだ、などと言いますが、スバシュは、ウダヤンならそれを聞いて鼻で笑ったかもしれない、などと考えてしまいます。ガンディーは人民の敵と結託した、自由の名のもとにインドから武器を奪った、と言うかもしれない、と。
スバシュは、マドラス出身のナラシムハンという経済学の教授とも知り合います。彼は実家が決めようとする花嫁候補をことごとく断り、アメリカ人の女性ケイトと結婚しました。そういう女性に実家がどういう反応をしたのだろうとスバシュは思います。スバシュはいずれ実家が決めた女性と結婚するのだろうことを疑っていません。そしてそのときは、トリー・ガンジに帰るときだと考えています。
スバシュのところにウダヤンから手紙が送られてきます。その手紙にはより左傾化したウダヤンの文章が綴られています。アメリカには(ベトナム)反戦運動がある、インドでは紅衛兵が組織されつつある、公正な社会に近づいているはずだ等など。そして、「兄貴がいないとつまらない。抱きつきたいくらいの弟より。」最後に引用の形で、「戦争は革命をもたらし、革命は戦争を終わらせる」と書かれていました。
一九七〇年に、スバシュにウダヤンから2通目の手紙が届きます。封書で写真が入っている、若い女性でした。自分はこの女性、名はガウリ、と結婚したのだというウダヤンの報告の手紙でした。このときのスバシュの心理は後の物語に影響すると思うので、ウダヤンの手紙の一部とスバシュの心理吐露の一部を書いておきましょう。
「正式に紹介できないので、写真を見せることにした。でも正式な通知だと受け取ってもらって構わない。そろそろ知らせてもいい頃かと思う。もう何年か付き合っている人だ。いままで黙っていたが、どういうことか見当はつくだろうね。ガウリという名前で、プレジデンシー大学の哲学科を卒業する見込みだ。北カルカッタのコーンウォリス通りに実家があって、両親ともに亡くなっている。家族は兄が一人と――この男が僕の友人なんだが――いくらか親類もいる。宝石やサリーよりも本を欲しがる人だよ。考え方も僕と同じだ。」(『低地』p66)
「ウダヤンは兄に先んじて結婚したのみならず、自分で選んだ女を妻にした。親が決めることだという観念を捨てきれないスバシュよりも、平気で前へ踏み出していた。またしてもウダヤンが先頭を進むという例だ。弟だから二番目だとは思いたくないらしい。いつものように自己流を通したがった。
写真の裏側にウダヤンの筆跡で日付が記されていた。一年以上も前だ。一九六八年。つまりスバシュがまだカルカッタにいた頃から、ウダヤンは恋人の関係を得ていたことになる。その間ずっと、ガウリのことを言わなかった。」(『低地』p67)
と、ここまでで1章が終わりです。68pまでのあらすじという感じで、いつもと書き方は変わらなかったような…。物語の方は大丈夫です。約470pありますから。この1章でインドの状況というのがだいたいわかってもらえたと思うので、導入としては成功していると確信して書いています。
「殺された弟。 その妻とともに 生きようとした兄。」
の帯のところまでも行っていないのでご安心を。たぶん、この記事を読んで重い政治的な話だと思われるかたがかなりいると思うのですが、そんなことはありません。このようなインドという生まれ故郷をバックボーンとして、家族がウダヤンをある形で失い、それをどう受け止め、そしてスバシュとガウリがアメリカに移住してから(ネタバレ?)どのような生活が待ち受けていたのか、もうひとつネタバレすると、ガウリはウダヤンの子どもを宿しています。もちろん、スバシュの両親はアメリカ移住も反対ですし、スバシュとガウリの結婚も反対です。その上ウダヤンの子どもまでいる。果たして、ベンガル人であるスバシュとガウリ、その子どもが、アメリカという国でいかに生き、どのような出会いと別れが待ちうけているのか。とてつもなく複雑な問題をテーマにして物語は進んでいきます。弟の妻と結婚したスバシュの決断、そしてそれを受け入れたガウリの決断がどのような結末を迎えるのか…。僕にとっては、超ヘビー級の作品でした。
しかし、ご安心ください。そこはジュンパ・ラヒリです。彼女の節度のある、そして上品な文章が読む人の助けとなってくれるでしょう。文章ひとつひとつが大切に紡がれているので、それほど苦痛に感じることはありません。むしろラヒリの紡ぐ言葉の数々に引き込まれるかたのほうが多いのではないかと。
結末はとても切ないものに仕上がっています。決して皆が共感するものとは言えないかもしれませんが、男女ともに、特に女性のかたはラヒリが女性なだけに、納得できる、せざるを得ない終わり方になっていると思います。読み終わった後の感慨は格別なものがあります。そしてタイトルの『低地』に込められた意味を僕たちは考えさせられることになります。
ということで、ジュンパ・ラヒリの『低地』の感想でした。うむ、感想というほどのものでもなかった…ただのあらすじ紹介に終始した気もしますが…
0 件のコメント:
コメントを投稿